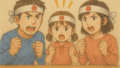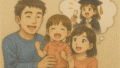小学校受験において、「学校別模試」はとても有効なツールです。
実際の入試を想定した形式で、自分の子どもがどこまで対応できるかを測ることができ、志望校の出題傾向を知る上でも貴重な情報源です。
ただし、受験予定の学校すべてで全日程を申し込んでしまうと、春以降は毎月のように模試漬けになり、時間も労力も奪われがち。
模試の受けすぎで「受けること自体が目的」になってしまっては、本末転倒です。
この記事では、模試を“ただ受けるだけ”で終わらせないための考え方と、志望校・併願校別に模試をどう活用すべきかを詳しく解説します。
模試を受ける目的は「現状把握」と「対策の指針作り」
模試を受ける本来の目的は、大きく2つに分けられます。
- 子どもがその学校の問題傾向にどこまで対応できているかの確認
- 今後の学習・対策に何を優先するべきかの判断材料
つまり、模試は“受けた後”に意味があるものです。
結果を見て、どこが弱点か、どの単元が未定着なのか、どの形式の問題で戸惑っていたのか。
そこを具体的に分析し、家庭学習や教室での対策に反映できるようにしてこそ、模試は本当に価値を発揮します。
志望校別:模試の受け方ガイド
第一志望校
最低2回は受けましょう。できれば時期をずらして。
1回目は春〜初夏(5〜7月)に。学校の傾向を知ることと、今後の対策ポイントを知るため。
2回目は秋(9〜10月)に、本番に近い環境での慣れと実力確認。
このように、「分析のため」と「仕上げ確認」の2軸で活用するのが理想です。
ただし、3回以上受ける場合は“同じ失敗を繰り返さない工夫”が不可欠。
模試の復習・振り返りを丁寧に行う余力があるか、必ず確認してください。
併願校
1回で十分です。対策の方向性がつかめればOK。
併願校は基本的に「合格できる安全校」であるべきですから、模試は「傾向把握」+「体験としての慣れ」を目的に、1回だけでよい場合が多いです。
また、併願校同士で出題傾向が近ければ、1校の模試を通じて複数校の対策に応用することも可能です。
模試の受験自体がストレスになりやすい子の場合、併願校の模試はあえて省略することも選択肢の一つです。
模試を“受けっぱなし”にしないために
模試の結果が返ってきたら、次の3つのステップで「活かす」ことを徹底しましょう。
1. 間違えた問題の単元をリストアップ
「この図形の回転、うちの子理解できてないな」
「お話の記憶で語彙が足りない」
など、出題形式ごとの理解度を見極めましょう。
2. 教室や家庭学習の教材で「苦手単元を繰り返す」
模試の復習だけで終わらせず、類題や応用問題に取り組むことがポイントです。
3. 模試の環境に慣れる
模試を重ねる最大の利点の一つは、「本番に似た空気感」への慣れです。
行動観察や面接形式がある模試なら、受けておくことで本番の緊張感が緩和されやすくなります。
模試の受けすぎで陥りやすい落とし穴
- 結果に一喜一憂しすぎて、子どものモチベーションが低下する
- 毎月模試を詰め込みすぎて、復習する時間が取れなくなる
- 模試の「点数」ばかりに目が向き、子ども自身の成長を見逃す
こうした事態を避けるためにも、模試は「厳選して」「目的を明確にして」受けることが大切です。
まとめ・結論
学校別模試は、志望校の傾向を知り、対策を練る上で欠かせないツールです。
しかし、「全部の学校・全日程受ける」必要はありません。
- 第一志望校は、目的を分けて2回程度が目安
- 併願校は、1回で十分。状況に応じては受けなくてもOK
- 受けた後は、復習・対策に活かすことが何より大切
模試はあくまで“道具”。上手に使いこなすことで、子どもの成長を確かに後押ししてくれます。