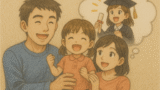小学校受験の準備に本格的に取り組む時期になると、多くのご家庭で悩むのが「習い事は続けるべきか?」「受験一本に絞るべきか?」という問いです。
子どもが習い事を楽しんでいる様子を見ると、無理にやめさせたくない。でも、受験の学習時間との両立を考えると不安もある――そんな葛藤は、決して珍しいものではありません。
ここでは、小学校受験と習い事を並行させることのメリットとデメリットを丁寧に整理し、それぞれの側面からどう向き合えばよいかを解説していきます。
習い事を続けるメリット
1. 「好き」や「得意」を育てるチャンスになる
子どもにとって習い事は、自分の個性や才能を発揮できる貴重な場です。ピアノ、スイミング、英語など、考査では評価されにくい分野であっても、「好き」や「得意」の土台を作ることは、将来の自信や自己肯定感につながります。
小学校受験では、面接や願書で「どんな子どもか」「どんな育てられ方をしてきたか」が問われることも多く、そうした場面で習い事のエピソードが「この子らしさ」を伝える材料になることもあります。
2. 学習以外のストレス発散になる
受験準備が本格化すると、どうしても机に向かう時間が長くなりがちです。そんな中、身体を動かす機会や、自由に表現する時間を確保することで、子どもが心身ともにバランスを保つことができます。
たとえば体操や水泳などは、全身運動によって脳を活性化させる効果もあり、結果的に学習の集中力向上にもつながるという報告もあります。
3. 社会性・協調性を育てる場になる
小学校受験の集団行動観察や行動観察テストでは、友だちとの関わり方、先生の指示の聞き方、協力姿勢などが見られます。
こうした力は、学習教室だけではなく、習い事の場――特にグループレッスンのような環境――で日常的に鍛えられることがあります。
たとえばスイミングやダンスの教室では、年齢の違う子どもたちと一緒に行動する中で、自然と「待つ」「譲る」「指示に従う」といった社会性が育ちます。
習い事を続けるデメリット
1. スケジュールが過密になり、疲れてしまう
一番多く聞かれるのが、「時間が足りない」「子どもが疲れてしまう」という声です。
平日は塾、週末は模試や行事、そこに習い事が加わると、結果として「子どもが自由に遊ぶ時間がない」「常に次の予定に追われている」という状態になりがちです。
【対策】
まずは、習い事の頻度や時間を見直すことが重要です。週2回通っていたものを週1に減らす、レッスンの時間帯を夕方から午前に変更するなど、子どもの生活リズムに無理がないように調整します。
また、年間スケジュールを立てる中で、受験期の直前(秋以降)は一時的にお休みするという選択も検討しましょう。
2. 勉強との「優先順位」にズレが出ることがある
子どもが習い事をとても楽しんでいる場合、受験勉強よりも習い事を優先したがることがあります。
特に「やりたくない勉強」と「楽しい習い事」が並ぶと、前者へのモチベーションが下がることも。
【対策】
「今は受験をがんばる時期」ということを、親子で丁寧に話し合い、目的と目標を共有することが大切です。
ただし、頭ごなしに「もう習い事はやめなさい」と言ってしまうと、子どもは反発してしまいます。代わりに、「習い事を続けるために、どう受験の準備と両立できるか」を一緒に考えるスタンスで接しましょう。
3. 教室の先生との連携が取りづらくなることも
習い事のスケジュールが塾や受験対策のクラスとかぶると、授業を欠席せざるを得なくなることも。
教室の進度に遅れてしまったり、大切な模試の前にリズムが崩れてしまったりする可能性もあります。
【対策】
習い事の予定は、必ず受験教室のスケジュールと照らし合わせて調整しましょう。
また、教室側には「この日は習い事で欠席します」と前もって伝えることで、配慮してもらえることもあります。
まとめ:習い事は「目的と効果」を意識して取り入れる
小学校受験と習い事の両立は、決して不可能ではありません。
小学校受験対策のベストセラー『小学校受験は戦略が9割』でも、特に新年中くらいまでは、習い事の継続を推奨しています。
大切なのは、「なぜ続けたいのか」「子どもにとってどんな意味があるのか」を親が明確に理解し、その上で、生活リズム・受験スケジュールとのバランスを丁寧に見直すことです。
習い事は、ただの“習慣”ではなく、子どもが好きなこと・得意なことに自信を持ち、心の豊かさを育てる貴重な時間でもあります。
受験勉強ばかりに偏らず、子どもが笑顔で毎日を過ごせるように、習い事も“我が家らしい受験スタイル”の一部として取り入れていきましょう。