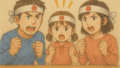小学校受験の準備を進めていると、「もうやりたくない」「できない」「やめたい」と、子どもが投げ出しそうになる瞬間に出会うことがあります。
そんなとき、親としてどんな言葉をかけるのが正解なのか、悩んだ経験はありませんか?
受験で求められるのは、単なる学力だけでなく、「我慢強さ」「粘り強さ」「あきらめずに取り組む姿勢」 といった非認知能力です。
これらの力は、行動観察などの場面でしっかりと見られています。
この記事では、子どもが「もうできない!」と投げ出しそうになったときに、親ができる声かけとサポートの方法 を、GRIT(やり抜く力)という視点から具体的に解説していきます。
「やり抜く力(GRIT)」とは?
GRITとは、「困難に直面しても、あきらめずに努力を続ける力」 のこと。
教育心理学者アンジェラ・ダックワースが提唱した言葉で、今、非認知能力のひとつとして大きな注目を集めています。
小学校受験でもGRITは大切
行動観察での「最後まで取り組む姿勢」、面接での「自分で考え、やってみる経験」、ペーパー試験での「難しい問題にも取り組む粘り」。
これらは「できなくても投げ出さない力」であり、まさにGRITです。
「もうできない!」子どもが投げ出すのはなぜ?
子どもが「もうできない!」と作業や学習を途中で投げ出してしまうことには、いくつかの理由があります。幼児期の子どもたちは、大人とは異なる感覚や限界を持っているため、背景を理解して対応することが大切です。
長く集中し続けるのがしんどくなったとき
幼児の集中力は発達段階に応じて限界があり、一般的には年齢+1分程度とされています(https://hoikushi-syusyoku.com/column/post_2034/)。
そのため、どんなに楽しい作業でも、長時間続くと集中が途切れ、疲れや飽きによって「もうできない」と感じることがあります。
この場合は、無理に続けさせるよりも、一度休憩を挟んだり、気分転換を図ったりすることが大切です。子どもの様子をよく観察し、適切なタイミングで休ませる工夫を心がけましょう。
自分の力では難しいと感じたとき
幼児は、ある課題に対して「できない」と感じると、それを「やめたい」という気持ちに直結させてしまいやすい特徴があります。まだ成功体験が十分に積み重なっていない幼児にとって、難しさを感じることはそのまま諦める理由になりやすいのです。
この段階では、子どもが「できない」と感じるハードルを少しずつ下げたり、小さな成功体験を積ませたりする工夫が必要になります。
頑張っても認められない、報われないと感じたとき
一生懸命取り組んだにもかかわらず、周囲から十分な承認や賞賛を得られなかった場合、子どもは「頑張っても意味がない」と感じ、意欲を失ってしまうことがあります。特に、途中まで頑張った過程が認められず、結果だけを評価されるような経験が続くと、「どうせできないならやめてしまおう」という思考になりがちです。
子どもの努力や成長のプロセスに目を向け、こまめに認め、褒めることが意欲の維持には不可欠です。
親ができる「投げ出しそうなときの声かけ」
子どもが「もうできない!」と投げ出しそうになったとき、親の声かけ一つで、子どもの気持ちは大きく変わります。無理に続けさせるのではなく、心に寄り添い、前向きな気持ちを引き出すことが大切です。ここでは、効果的な声かけのポイントをご紹介します。
子どもの気持ちをまず受け止める
子どもが苦しんでいるときに否定的な言葉を投げかけると、さらに自信を失い、やる気をなくしてしまいます。
NG例:「また途中でやめるの?」「だからできないのよ」
OK例:「難しかったね」「頑張っていたの知ってるよ」
まずは子どもの努力や悔しい気持ちに共感を示しましょう。共感の言葉をかけるだけで、子どもは安心し、落ち着きを取り戻します。気持ちを受け止めることが、次への一歩を踏み出すための土台になります。
小さな成功に目を向けさせる
全体の完成を目指すのではなく、途中までできたことを肯定的に伝えると、子どもの自己肯定感が育まれます。
声かけ例:「ここまではできたよね、すごいよ」「あと少しで終わるよ、一緒にやってみようか」
できたところに焦点を当てることで、「自分にもできる」という感覚を持つことができます。小さな成功体験を積み重ねることが、次のチャレンジへの前向きな気持ちにつながります。
「チャレンジする姿勢」を褒める
結果ばかりに目を向けると、子どもは「できなかった=ダメ」と感じてしまいがちです。大切なのは、挑戦しようとしたその姿勢を認めることです。
声かけ例:「最後までやってみようとしたのがえらかった」「やってみようと思ったことが、すごいんだよ」
たとえ途中で終わったとしても、チャレンジしようとした勇気や意欲を褒めることで、やる気の土台を育むことができます。
一緒に区切りをつける
子どもの集中力や気力には限界があります。無理に続けさせるのではなく、適切な区切りを設けることも大切です。
声かけ例:「ここまで頑張ったから、5分休憩しよう」「今日はここまででOK。次はここからね」
無理にやりきらせるよりも、自分で「ここまでやった」と満足できる体験を重ねることが、次に取り組む意欲につながります。区切りをつけることで、子ども自身も気持ちを切り替え、リフレッシュできます。
GRITを育むために、日常生活でできること
1. 「頑張るって気持ちいいね」を体験させる
- ブロックで少し難しい作品を完成させる
- パズルを何日かかけてやりきる
- お手伝いを「最後まで一人でやってみる」
達成感を味わえる小さなチャレンジを、日常の中でつくりましょう。
2. プロセスを褒める声かけを習慣に
- 「どうやって考えたの?」
- 「工夫したところ、教えて」
「結果ではなく、過程を認める」ことで、挑戦する姿勢が育ちます。
3. 目標を「小さく」「具体的に」設定する
- ×「全部できるようにしよう」
- ○「今日はここまでやってみよう」
小さな成功体験が、自信とGRITを育てます。
4. 親が見せる「諦めない姿勢」も大切
- 家事や仕事を丁寧にやる姿を見せる
- 「ママもちょっと苦手だけど、頑張ってみるね」と伝える
親の姿勢は、子どもにとって最大の学びになります。
まとめ:投げ出しそうな時こそ、成長のチャンス
子どもが「もうできない」と言ったときの対応ポイント
✅ まず気持ちを受け止める
✅ 小さな成功や努力を認める
✅ 結果ではなく、挑戦する姿勢を褒める
✅ できる範囲で区切りをつけて、前向きに終える
子どもがくじけそうになったとき、ただ「がんばりなさい」と言うのではなく、 「一緒に乗り越えよう」という気持ちで寄り添ってあげることが、やり抜く力を育てる土台になります。