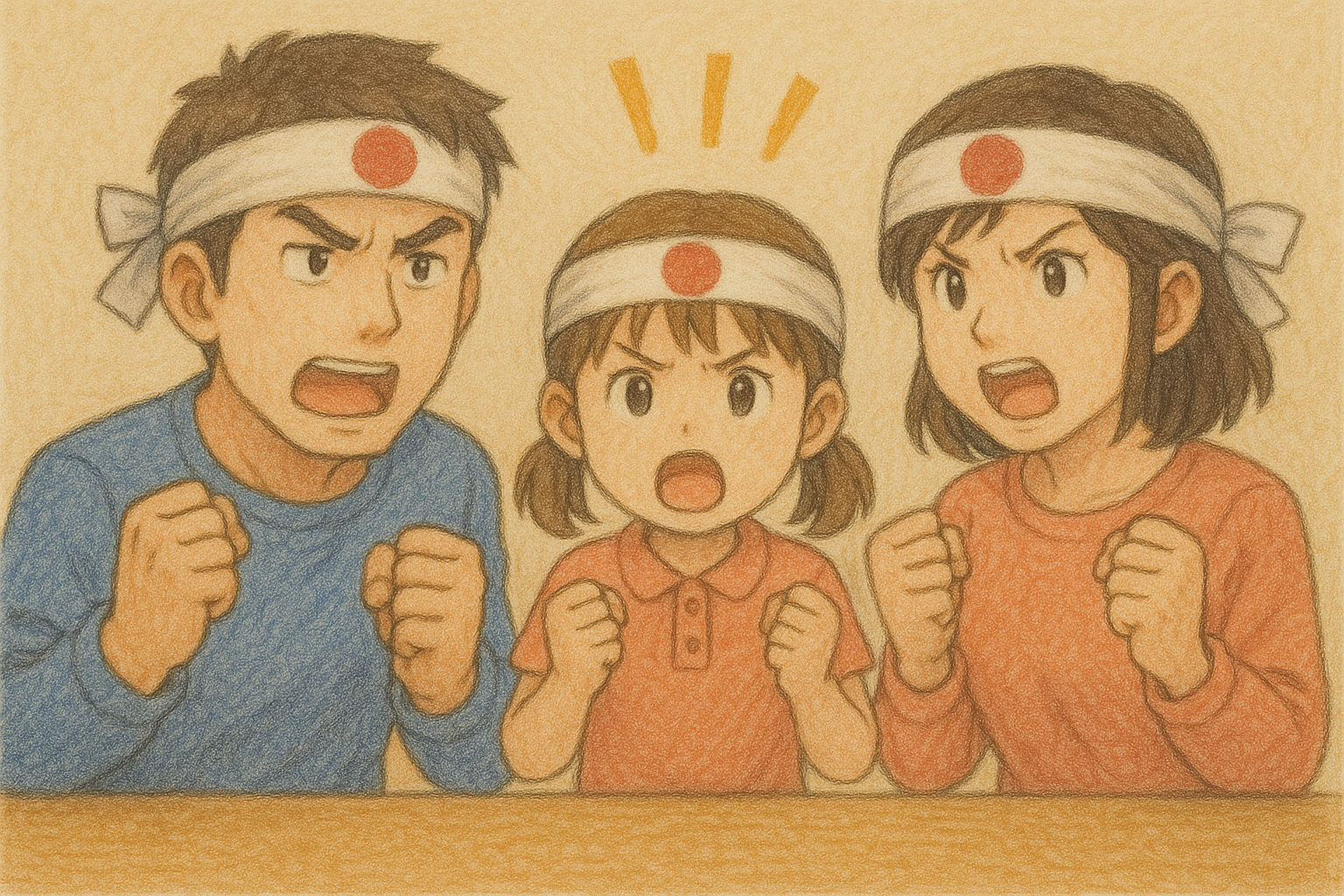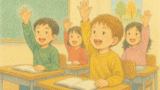「小学校受験をする」と決めることは、単に“学校を選ぶ”という意味ではありません。
それは、家庭の時間の使い方、教育に対する姿勢、家族全体の生活スタイルまでもが変わる覚悟を持つということでもあります。
この記事では、小学校受験を決めたご家庭がまず「知っておくべきこと」「覚悟しておくべきこと」、そしてその先にある困難をどう乗り越えていくのかを、実際の経験も交えながらお伝えします。
覚悟①:親の時間とエネルギーが大きく求められる
小学校受験では、まだ幼い子どもだけに努力を求めることはできません。親の関与は“主役級”だと考えておいた方がよいでしょう。
送り迎え、家庭学習のサポート、模試や面接の付き添い、願書の作成…そのすべてに「手間」と「時間」と「精神力」が求められます。
特に共働き家庭では、誰がどの役割を担うのか、スケジュール管理はどうするのかを具体的に話し合い、役割分担していくことが重要です。
我が家では当初から、小学校受験を“チーム戦”のように位置付け、パパとママのどちらかに負担が偏らないように気を配ってきました。1人がすべて抱え込むと、必ず疲弊します。模試の送迎や家庭学習の丸つけなど、うまく分担したいですね。
覚悟②:金銭的な負担は避けられない
大手塾の月謝、模試、特別講習、教材費、交通費…。小学校受験にはある程度の経済的余裕が必要です。
年間でかかる費用は、平均して60万〜120万円、トータルでは数百万円とも言われています(https://www.happy-clover-ojuken.jp/blog/%E3%81%8A%E5%8F%97%E9%A8%93/6019/)。
さらに、受験校が複数あれば、入学手付金や入学の権利を保持しておくために払っておく入学金の用意も必要になることがあります。
大切なのは、「どこにどれだけかけるか」を明確にし、無理のない範囲で“戦略的に投資”することです。
たとえば、苦手分野だけ個人指導を追加する、模試は志望校のものだけに絞るなど、優先順位をつけて資金配分を考えることが求められます。
覚悟③:思い通りにいかない“伸び悩み”や“壁”が来る
最初は順調に見えていたのに、ある時から突然問題が解けなくなった、模試の成績が落ちた、子どもが学習に後ろ向きになってきた――。
そうした“伸び悩み”は、ほとんどのご家庭が経験します。
大事なのは、結果だけを見て一喜一憂せず、プロセスを見守る目を持つこと。
ある先輩家庭からこんな話を聞いたことがあります。
夏の模試で順位が落ち、正直焦りました。でも、塾の先生から「ここで焦って叱ったら、子どもの気持ちが離れてしまう」と言われ、思い切って1週間、完全に学習を休ませました。再開後は自分から机に向かうようになり、あの休息が実はすごく効いていたと思います。
覚悟④:子どもの個性と志望校の“ずれ”に悩む時期が来る
憧れの難関校に入れたい。でも、その学校の求める「理想の子ども像」と、わが子の個性に違和感を覚えたとき、親として進路を再考するタイミングが来るかもしれません。
早稲田実業学校初等部や慶應義塾幼稚舎などの人気校は、知的能力だけでなく、自立心や行動力、品位といった人格面も求めます。
子どもがその教育方針にフィットするかどうかは、説明会や模試を通して実感することが多いのです。
無理に合わせようとすると、親子ともに苦しくなってしまうこともあります。「うちの子らしく育てること」と「学校の理想像」との間で、どう折り合いをつけるかは、受験期最大の選択のひとつです。
困難をどう乗り越えるか?3つの方針
1. 情報を整理し、“わが家軸”を持つ
あれもこれも…と惑わされるのではなく、「なぜ小学校受験をするのか」「わが子にとって最適な環境は何か」を家族で言語化しておくこと。
この“わが家の軸”があるだけで、迷ったときの判断がぶれません。
2. 完璧を目指さない
すべてを100点でこなそうとすると、親が燃え尽きてしまいます。「8割で合格」と割り切り、適度に力を抜く習慣も必要です。
子どもも、頑張っている親の姿を見て育ちますが、“疲れた顔”を見続けることは逆効果になることも。
3. 仲間を作る
お受験は孤独になりがちですが、同じ立場の親とのつながりが心の支えになることがあります。
教室でできたママ友・パパ友との小さな情報交換、励まし合いが、時に大きな安心感に変わることも。
まとめ・結論
小学校受験を決めた瞬間から、親子で乗り越えなければならない現実がいくつも待っています。
時間、費用、子どもの成長、家庭内のバランス…。それらを乗り越えるには、「覚悟」と「柔軟な姿勢」が必要不可欠です。
けれど、親がしっかりと見守り、励まし、支えてあげることで、子どもは確実に成長します。
そして、受験の結果以上に、“親子で歩んだ時間”が、何よりの財産になるはずです。